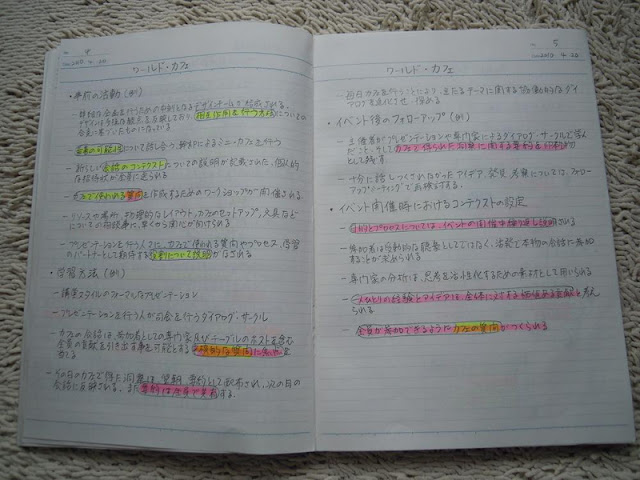この図でピンクで表された線により他のブランチに関連付けられています。これが、マインドマップでは重複するアイデアをどこか1つにまとめるのだと思います。ですから、マインドマップでは中心から書き始めるというアイデアに3色以上でというのがなくなっています。以下が、同じ図をマインドマップであらわしたものです。
以下の図は、マインドマップでもアイデアマップでもなく、上記図の構造を考える上で文章化したものです。マインドマップにしろアイデアマップにしろ、メインブランチのまとめ方が右から左への時計回りで思いつくものを1語であらわしてゆきます。「アイデアマップ」の著者は一般的にメインブランチが、なぜ、このような言葉だったかの理由は分からないそうです。だた、思い浮かんだだけで、思いつくままに書いたりします。順序は後から考えればよいようです。
一回りするメインブランチは5から9本がよいそうです。しかし、その中身は時系列に動作を記述したり、同じカテゴリーでまとめたり、異なるカテゴリだったりまちまちです。わたしは、この例が、末端のブランチから見てくると、「どのように」、「何を」、「どうする」となっているように読み取れますが、これが基本かどうかは分かりません。
では、この図を使って「アイデアマップの法則」について、説明します。アイデアマップは白い紙を用意して紙を横向きに置き、3色以上を使って中心から紙に書き始めます。3色以上で色分けしたり、立体感のある図を使ったり、シンボルを使ったり、ユーモアの有る図を使ったイメージを使います。ブランチには1語で表される語を楷書体で言葉を使います。論理は開放型でメインブランチをあらわし、各ブランチは更に枝を伸ばしてゆく流れ型で表して表現します。
さて、実際のグループ対話で利用するには、聴きながら書き進めなければならないので、熟練が必要です。「アイデアマップ」の第13章リアルタイム・アイデアマッピングでは、対話しながらその場で書き出すという、分類せず、思いつくままなので、あとで整理をしたほうがよいようです。
Visionary Institute - 2010の索引ページに戻る